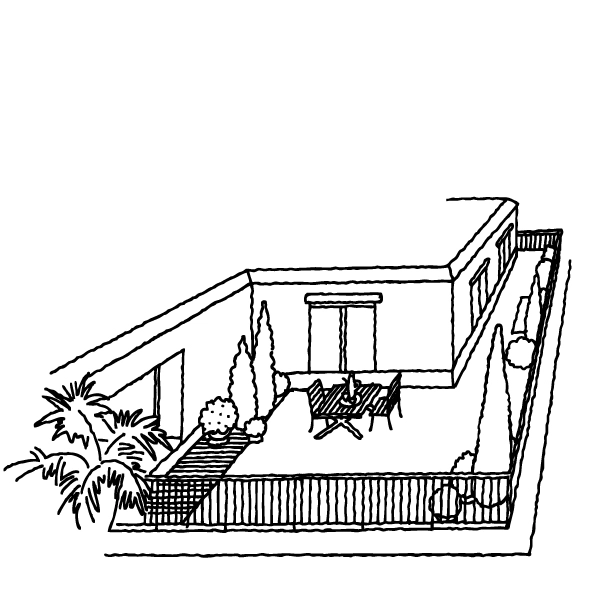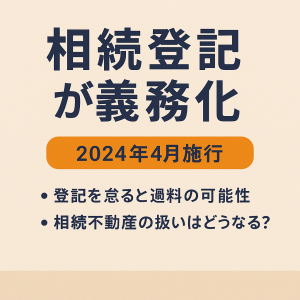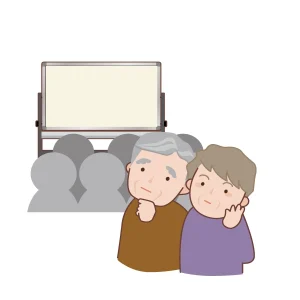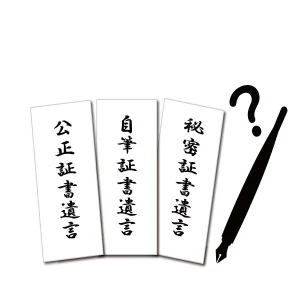不動産を生前贈与したいと考えたときに、まず気になるのが「誰に贈与できるのか」という点ではないでしょうか。子どもや配偶者はもちろん、孫や兄弟姉妹なども対象になるのか、そして贈与税はどうなるのか。
こうした疑問は多くの方が抱える共通の悩みです。
不動産の生前贈与対象者はどこまでなのか。本記事ではその範囲をわかりやすく整理し、贈与できる人の範囲や対象者ごとの税金の注意点について解説します。
相続トラブルを避け、安心して資産を引き継ぐための基礎知識としてぜひご活用ください。
不動産の生前贈与の対象者は誰まで?
不動産の生前贈与は、基本的に誰にでも行うことが可能です。
法律上は相手が家族でなくても贈与契約を結べば成立します。ただし、贈与税の負担や将来の相続トラブルを考えると、対象者の選び方が非常に重要になります。
ここでは、一般的に選ばれる範囲と、家族以外に贈与するケースについて整理していきます。
一般的に生前贈与の対象となる範囲
不動産の生前贈与は、多くの場合「家族」に対して行われます。
特に以下のケースが一般的です。
子ども(直系卑属)
最も多いのが、親から子どもへの贈与です。将来の相続を見据えて早めに不動産を移転しておくことで、スムーズに資産承継が進められます。
贈与税の「相続時精算課税制度」などを活用できるのも大きなメリットです。
孫
近年では、孫への生前贈与も増えています。
教育資金や結婚資金と合わせて不動産を贈与するケースもあります。
ただし、孫は「一世代飛ばし」です。
そのため、相続税の計算上、子どもよりも負担が大きくなる可能性がある点に注意が必要です。
配偶者
配偶者への贈与は、居住用不動産について「配偶者控除(最高2,000万円までの特例)」を利用できます。長年連れ添ったパートナーに住まいを残す形で贈与する方も多く見られます。
家族以外にも贈与できるのか?(兄弟姉妹、甥姪、第三者)
不動産の生前贈与は、家族以外にも可能です。例えば、兄弟姉妹、甥や姪、さらには親族以外の第三者へも贈与できます。しかし、これらの場合は注意が必要です。
- 兄弟姉妹・甥姪
- 贈与自体は可能ですが、子や配偶者と異なり特別な控除はありません。そのため、贈与税の負担が大きくなりやすい傾向があります。
- 第三者
- 法的には問題なく贈与できますが、親族以外に不動産を移転すると、後の相続時に家族間でトラブルになるリスクもあります。
したがって、家族以外に贈与する場合は、税金面と相続関係の両方を十分に検討しましょう。
必要に応じて専門家に相談することが大切です。
対象者ごとの注意点
不動産の生前贈与は、贈与する相手によって税金の扱いや将来の相続への影響が変わります。
誰に贈与するかを考える際は、単に「渡したい人」に贈るのではなく、制度や税負担を理解したうえで計画的に判断することが重要です。
子どもに贈与する場合
子どもへの不動産贈与は最も一般的です。
利用しやすい制度として「相続時精算課税制度」があり、2,500万円まで非課税で贈与できます。
この制度を使えば早めに財産を移転しつつ、相続時に精算する形が取れます。そうすることで、相続全体を見据えた資産承継に有効です。
ただし、一度この制度を選ぶと暦年課税へ戻せないため、事前の検討が欠かせません。
孫に贈与する場合
孫に不動産を贈与するケースでは、税務上の注意が必要です。
子どもを飛ばして孫に直接贈与すると「一世代飛ばし」となります。
相続税の負担が増える「世代間課税」の対象になることがあります。
教育資金や結婚資金の非課税制度を組み合わせることもできますが、不動産贈与では特に慎重な判断が求められます。
配偶者に贈与する場合
配偶者に不動産を贈与する際は「配偶者控除」の特例を活用できます。
婚姻期間が20年以上であれば、居住用不動産について2,000万円まで贈与税がかからずに移転可能です。
これは、長年住んできた自宅を安心して残す手段として有効です。配偶者控除は一生に一度(婚姻20年以上などの条件が必要)しか使えないため、タイミングを誤らないことが大切です。
兄弟姉妹や第三者に贈与する場合
兄弟姉妹、甥姪、友人などの第三者に不動産を贈与することも法律上は可能です。
しかし、直系卑属や配偶者に比べて税制上の優遇がなく、贈与税の負担が重くなりやすい点に注意が必要です。
また、親族以外に贈与する場合は、後々の相続で他の相続人とのトラブルを招くリスクもあります。
こうしたケースでは必ず事前に専門家へ相談することをおすすめします。
不動産を贈与する際に気をつけたいポイント
不動産の生前贈与は、資産承継の有効な手段です。しかし、注意すべき点を理解していないと税負担が増えたり、相続人同士のトラブルにつながったりします。
ここでは、特に押さえておくべきポイントを4つ紹介します。
贈与税の基礎控除と評価額の計算
不動産を贈与する場合、贈与税の基礎控除(年間110万円)を超える部分に贈与税がかかります。
さらに、不動産は「時価」ではなく、固定資産税評価額や路線価をもとに評価されるのが一般的です。
評価額の算定方法を誤ると、予想以上の税負担になることがあるため、専門家に確認しておくと安心です。
複数相続人がいる場合の公平性の確保
不動産は現金と違い分割しにくいため、特定の相続人だけに贈与すると相続時の不公平感を招くことがあります。
例えば、長男に自宅を贈与した場合、次男・三男が不満を抱くケースは少なくありません。
生前贈与を行う際には、将来の分配方法も含めて家族全体で話し合い、公平性を意識することが大切です。
登記などの法的手続きの必要性
不動産の贈与は「口約束」では成立しません。
贈与契約書の作成に加えて、必ず名義変更の登記手続きが必要です。
登記を怠ると、後に贈与の事実を証明できなくなったり、相続の際にトラブルになったりする恐れがあります。司法書士や専門家に依頼して確実に手続きを行うようにしましょう。
将来の相続トラブルを避けるための事前準備
生前贈与は、相続の一部を前倒しして行うものです。
そのため、事前に遺言書の作成や遺留分(相続人が最低限受け取れる取り分)の確認をしておくことで、相続発生後のトラブルを防げます。
特に不動産は大きな資産となるため、贈与前に家族で話し合い、専門家に相談することがトラブル回避につながります。
不動産の生前贈与対象者は計画的に選ぶ
不動産の生前贈与は、子どもや孫、配偶者など家族を中心に幅広い対象者に行うことが可能です。
しかし、誰に贈与するかによって税制上のメリットや負担、将来の公平性に大きな違いが出ます。
特に「子ども」や「配偶者」への贈与は制度上の特例が用意されていますが、それ以外の兄弟姉妹や第三者への贈与では税負担が大きくなるため、注意が必要です。
また、不動産は分割しづらい資産であるため、相続人間の不公平感を招かないように配慮しながら計画を立てることが大切です。
早めに準備を進め、専門家のアドバイスを得ながら進めることで、家族の負担を軽減し、安心した資産承継につながります。
関連記事:小規模宅地等の特例 | 不動産相続で相続税を最大80%軽減する方法について
まずは専門家にLINEで気軽に相談してみませんか?
不動産の生前贈与は、対象者の選び方ひとつで税金の負担や将来の相続トラブルに大きな差が生まれます。インターネットで調べてもケースごとの判断は難しいものです。
当社では、経験豊富な相続の専門家が無料でご相談を承っています。まずは公式LINEにご登録いただき、気になることをメッセージでご相談ください。
- 不動産を誰に贈与するのが最適か知りたい
- 贈与税や控除について詳しく聞きたい
- 相続時のトラブルを避ける方法を知りたい
LINEなら いつでも・どこでも気軽に相談 できます。
ぜひ今すぐ、下記のリンクからご登録ください。