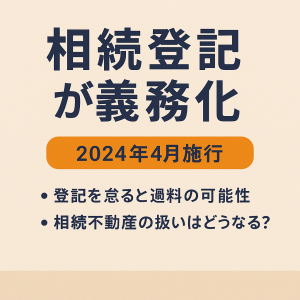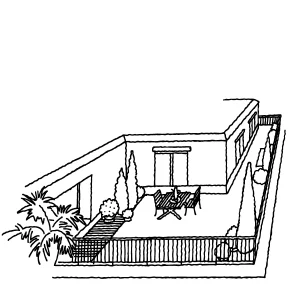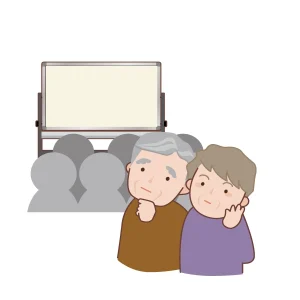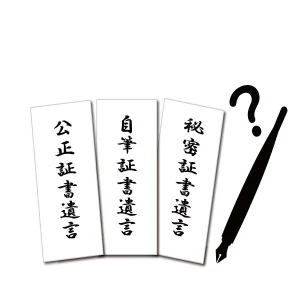不動産相続で家族信託を活用する方法とそのメリットについて今回は紹介していきます。
家族信託は、親(委託者)が信頼できる家族(受託者)に不動産の管理や処分の権限を託す仕組みで、元気なうちから“もしも”に備えられる相続対策として注目されています。
遺言や成年後見制度とは違い、柔軟な資産管理ができる点が最大の魅力です。
この記事では、家族信託が相続にどう役立つのか、そして活用すべきケースや注意点まで。これらの内容についてわかりやすく解説します。
相続で失敗しないための一歩として、ぜひ参考にしてください。
そもそも家族信託とは?【相続対策の新しい選択肢】
「家族信託」とは、家族内で信頼できる人に財産の管理・運用を託す制度です。特に不動産の相続対策として近年注目されており、将来のトラブル回避や柔軟な資産管理が可能になります。
遺言や成年後見制度と比べて自由度が高く、「認知症になった後の財産管理」や「複数世代にわたる資産承継」などに対応できる点が強みです。
ここでは、家族信託の仕組みや他制度との違いを具体的に説明していきます。
家族信託の基本構造(委託者・受託者・受益者)
家族信託は、主に以下の3者によって成り立ちます。
- 委託者(親など):財産を持ち、信託を設定する人
- 受託者(子など):信託された財産を管理・運用する人
- 受益者(親本人 or 家族):信託財産から利益を受ける人
たとえば、高齢の親(委託者)が、自宅やアパートなどの不動産を子ども(受託者)に託し、自分自身(受益者)のために運用・管理してもらうといったケースがよくあります。
この仕組みを使うことで、親が認知症になった場合でも、子どもが不動産の売却や管理などの手続きをスムーズに進めることができます。
遺言・成年後見制度との違い
家族信託と混同されがちな制度に「遺言」と「成年後見制度」があります。しかし、この2つの仕組みは、それぞれ特徴が異なります。
- 遺言は、亡くなった後に効力が発生するもので、生前の資産運用や管理には使えません。
- 成年後見制度は、認知症などで判断能力が失われた人をサポートする制度です。しかし、家庭裁判所の監督がつくため、資産運用の自由度は低くなります。
一方で家族信託は生前から機能し、かつ柔軟に資産を管理・承継できるという点で、他の制度にはないメリットがあります。
関連記事:終活の新常識!家族信託の活用で安心の相続計画を実現する方法
家族信託が相続に有効な理由
「相続トラブルを避けたい」「親が認知症になる前に備えたい」と考える方にとって、非常に効果的な対策となるのが家族信託です。従来の遺言や成年後見制度だけではカバーできない課題に対応できる点が、家族信託の大きな魅力です。
ここでは、相続対策として家族信託が有効な3つの理由について、具体的に解説します。
認知症対策になる(財産凍結を防ぐ)
高齢の親が認知症を発症すると、名義人である親の財産(不動産や預貯金)は基本的に「凍結状態」となり、売却や運用ができなくなります。
この状態に陥ると、成年後見制度を利用しなければなりません。そして、家庭裁判所の監督が入るなど手間や制限が増え、家族の負担も大きくなります。
一方、家族信託を活用しておけば、認知症発症後も受託者(たとえば子ども)が財産を管理・活用できます。そのため、不動産の売却や修繕、賃貸運用などがスムーズに行えます。つまり、将来の財産凍結リスクを防ぐことができるのです。
柔軟な資産承継が可能(2次相続・3次相続まで設計できる)
家族信託のもう一つの魅力は、「次に誰に財産を渡すか」を複数段階にわたって設計できる点です。
たとえば、
- 親(委託者・受益者)
- 長男(第2受益者)
- 長男の子ども(第3受益者)
といった具合に、2次相続・3次相続の内容まであらかじめ決めておくことが可能です。
通常の遺言では、1回の相続しか指定できません。しかし、家族信託なら相続が発生した後の相続についても柔軟にコントロールできます。
このように家族信託は、財産の流れを意図したとおりに運ぶことができるのです。
遺産分割協議を不要にし、トラブルを未然に防ぐ
相続発生後、法定相続人全員による「遺産分割協議」が必要になります。実は、この遺産分割協議がトラブルの大きな火種になることも少なくありません。
たとえば、
- 「長男ばかりが得をしている」
- 「親の面倒を見ていた人に全部渡すのは納得できない」
このような不満が噴出し、家庭内の対立に発展するケースもあります。
しかし、家族信託で不動産や財産の管理・承継方法を事前に決めておけば、相続発生後の分割協議が不要になり、親族間の争いを回避することができるのです。
「親の想いを形にしておく」ことが、将来の家族の平穏にもつながるのです。
★関連記事:遺産分割協議の基本と協議書の書き方|注意点・記載例を紹介
不動産相続で家族信託を活用する具体例
家族信託は、不動産を含む財産をスムーズに管理・承継するための有効な手段です。特に相続にまつわる「ありがちな不安」や「実際に起きがちなトラブル」に対して、具体的な対策を講じられるのが大きな魅力です。
ここでは、不動産相続で家族信託が役立つ代表的な3つのケースをご紹介します。
ケース① 親が認知症になってしまった後に困らないために
【状況】
80代の父親が自宅とアパート1棟を所有。今は元気だが、最近物忘れがひどく、家族は将来の認知症リスクを心配している。
【課題】
父が認知症になってしまうと、不動産の名義人としての判断能力がなくなり、
- アパートの修繕や契約更新
- 売却や建て替え
などの手続きが一切できなくなる。
【家族信託の活用】
家族信託契約を事前に結び、「父を委託者・受益者」「長男を受託者」とすることで、父の意思能力が失われた後も、長男がアパートを管理・売却する権限を持てるように。
これにより、認知症による“財産の凍結”を未然に防げます。
ケース② 子どもに引き継がせたいが揉めるのが心配なとき
【状況】
母親が亡くなり、父親が一人で不動産を相続。自宅と賃貸アパートを持っているが、相続人は3人の子どもたちで、兄妹仲がやや険悪。
【課題】
父親の死後に遺産分割協議を行うと、財産分配をめぐって兄妹間で争いになるリスクがある。自宅を長女に、アパートを長男に…と考えていても、実行は難しい。
【家族信託の活用】
父が生前に家族信託契約を結び、
- 自宅は長女に承継
- アパートは長男が管理・収益を得る
と財産の承継方法をあらかじめ明文化。
家族信託では遺産分割協議が不要となるため、感情論による争いを避け、円満な財産承継が可能になります。
ケース③ 空き家や収益不動産を将来的に売却させたいとき
【状況】
親が相続で得た空き家を「そのうち売る」と言っていたが、何年もそのまま放置。管理費や税金だけがかかっている。
【課題】
このままでは空き家が老朽化し、資産価値も低下。いざ売ろうとしても、親の判断能力が低下していたら不動産売却自体ができなくなる。
【家族信託の活用】
親が元気なうちに家族信託契約を結び、
- 空き家を信託財産とする
- 子どもを受託者とし、適切なタイミングで売却可能に
こうすることで、親が判断できなくなった後でも、子どもが空き家を売却し資金化する判断が取れるようになります。老朽化や空き家特例など、タイミングを逃さず動けることが最大のメリットです。
家族信託の進め方と注意点
家族信託は自由度の高い相続対策ツールですが、その設計や実行には注意すべき点も多くあります。仕組みの柔軟さゆえに、誤った設計や法的・税務上の理解不足がトラブルを招くケースも。
ここでは、家族信託をうまく進めるためのステップと注意点をわかりやすく整理してご紹介します。
家族信託の設計ステップ(目的・人選・信託契約)
まず重要なのは「なぜ信託をするのか?」という目的を明確にすることです。単なる節税ではなく、たとえば以下のようなニーズが出発点になります。
- 親が認知症になる前に財産管理を委ねたい
- 子どもたちの間で相続トラブルを避けたい
- 特定の資産を特定の子に確実に引き継がせたい
そのうえで、「委託者(財産の持ち主)」「受託者(財産を預かって管理する人)」「受益者(利益を受け取る人)」という3者の関係を整理し、信頼できる受託者を選ぶことが重要です。
設計が固まったら、信託契約書を公正証書で作成し、内容を法的に明確にします。
不動産信託で必要な登記や税務上の確認事項
不動産を信託財産とする場合、信託登記を行う必要があります。信託契約だけでは名義変更は完了せず、登記簿に「信託による所有権移転」が記載されなければなりません。
また、家族信託では、
- 固定資産税や相続税の扱い
- 収益不動産であれば所得税の申告
など、税務上の確認が不可欠です。
特に、不動産の評価方法や課税タイミングについては、事前に税理士などの専門家と協議することで、後のトラブルや予期せぬ課税を避けることができます。
税理士・司法書士・弁護士など専門家の関与が成功のカギ
家族信託は遺言や成年後見制度に比べて自由度が高い反面、民法や信託法、不動産登記法、税法など多くの法分野にまたがる知識が必要になります。
そのため、以下のような専門家の関与が不可欠です。
- 税理士:節税設計・所得税・相続税への影響を判断
- 司法書士:信託登記・名義変更手続きの実務をサポート
- 弁護士:信託契約の妥当性や家族間の調整、将来の紛争防止
専門家が入ることで、法的にも税務的にも安定した信託設計が可能となります。そして、その結果、思わぬ抜けや誤解を防ぐことができます。
家族信託を検討すべきタイミングとは?
家族信託は「将来の不安に備える仕組み」である以上、できるだけ早めの準備がカギになります。よくある誤解のひとつに「認知症になってから考えればいい」というものがあります。しかし、これは大きなリスクです。
ここでは、家族信託を導入するのに適したタイミングを3つの代表的なケースに分けて解説します。
親がまだ元気なうちに始めるのが理想
家族信託を行うには、委託者(財産を信託する人)が契約内容を理解して判断できる状態である必要があります。
つまり、認知症などによって意思能力を失った後では、信託契約そのものが結べません。
そのため、次のような兆しが出てきた段階で、すでに準備を始めるのが望ましいです。
- 親が高齢になってきた
- 財産の整理について話し合える状態である
- 何らかの病気が進行しているが、まだ判断能力はある
「いざというときに困らないように」という視点での早めの信託設計が、円滑な財産管理につながります。
相続人が複数いて不動産を共有しそうなとき
不動産は分けにくい資産の典型であり、複数人で共有相続した結果、意思決定ができず塩漬けになるケースが多発しています。
たとえば、
- 「売却したい人」と「残しておきたい人」で意見が分かれる
- 使用料や固定資産税の負担割合をめぐって対立する
- 相続登記を放置したまま、さらに次世代に承継されてしまう
こうした事態を避けるために、生前の段階で家族信託によって管理者(受託者)を一本化しておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。
収益不動産を管理・売却しながら引き継ぎたい場合
アパート・貸家・テナントビルなどの収益不動産を相続予定の場合も、家族信託は非常に有効です。
というのも、収益不動産は次のような課題を伴います。
- 認知症になると賃貸契約や修繕の意思決定ができなくなる
- 管理や入居者対応を子どもが引き継ぎたくても、所有者が本人のままでは権限がない
- 将来的に売却したい場合、本人の意思確認ができず困難になる
これらのリスクに備えるため、信託により所有権を形式的に移し、子ども世代が管理・運営・売却の判断を行える体制を作ることが大切です。
家族信託で「もめない」「困らない」相続を実現しよう
相続は「財産をどう分けるか」だけでなく、「どう管理し、どのように次世代に引き継ぐか」までを見据えた準備が大切です。
特に、不動産や収益物件など分けにくい資産がある場合は、遺言や成年後見制度だけでは対応が不十分になることもあります。
そんなときこそ、家族信託という選択肢が力を発揮します。
契約によって「いつ・誰に・どのように」財産を託すかを柔軟に設計できるため、認知症による資産凍結や、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。
大切なのは、「何かあってから」ではなく、「何もない今」から準備を始めることです。
家族の未来を守るためにも、専門家の力を借りながら、円満で計画的な相続対策を進めていきましょう。
LINEで無料相談受付中!
「家族信託ってうちのケースでも使える?」という方へ
相続や不動産の引き継ぎ、将来的な管理でお悩みの方に向けて、LINEで気軽に専門家へ無料相談できる窓口をご用意しています。
- 親が元気なうちに準備を始めたい
- 相続で家族が揉めないようにしたい
- 不動産をどう活用すべきかアドバイスがほしい
…といったご相談にも対応可能です。
👉 [LINEで無料相談する]
迷ったら、まずは一歩。家族の安心と円満な相続のために、こころわにご相談下さい。