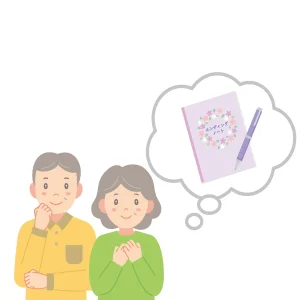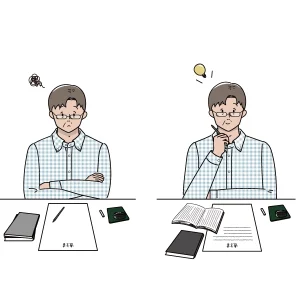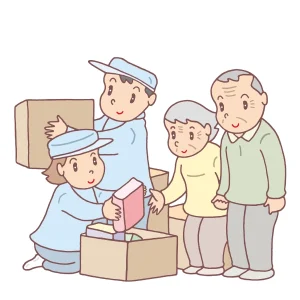「エンディングノートって、まだ早い気がして書く気にならない」
そんなふうに感じている方は少なくありません。実際、「まだ元気だから」「年老いてから考えればいい」と先送りしてしまうケースも多くあります。
けれど、人生にはいつどんなことが起きるか分かりません。事故や急な病気、意思を伝えられなくなる瞬間は、ある日突然やってくるかもしれないのです。
そんな時、あなたの“想い”や“希望”が何も残されていなかったら、残された家族は、何をどう判断し、どんな選択をすればよいのでしょうか?
ここで活躍するのが、エンディングノートです。
これは「死の準備」ではなく、「自分らしい人生の締めくくり」を考えるためのツール。
遺言書のような法的な効力はありませんが、もっと自由に気軽に、自分の気持ちを記録することができるノートです。
- 財産のこと
- 医療や介護の希望
- 家族へのメッセージ
“未来の自分”と“大切な人”のために、今できる備えを一緒に始めてみませんか?
このブログでは、エンディングノートの書き方や記載内容、保管方法、そして続けるコツまで、わかりやすく解説していきます。
「まずは何から始めればいいの?」という方にも役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
エンディングノートとは?まず知っておきたい基礎知識
「エンディングノート」と聞くと、「まだ自分には関係ない」と感じる方も多いかもしれません。
しかし、エンディングノートは終末期だけのものではなく、元気なうちから始められる“人生の備え”として注目を集めています。
エンディングノートには、家族への思い、医療や介護に関する希望、財産に関する情報など、自分の意思を自由に記しておくことができます。万が一、自分が意思表示できなくなったときでも、ノートがあることで家族がスムーズに判断・対応できるようになります。
ここでは、エンディングノートの目的と、よく混同されがちな遺言書との違いについて分かりやすく解説します。
エンディングノートの目的とは?
自分の意思を伝えるためのノート
エンディングノートの最大の目的は、「自分の想い」や「希望」を大切な人に伝えることです。
たとえば、
- 延命治療についての希望や、
- 認知症になった際の介護方針、
- 葬儀の形式や連絡してほしい人のリスト
など、突然の事態でも周囲が困らないように、あらかじめ自分の意思をノートに書き留めておくのです。
法的な効力はないものの、ノートに書かれた言葉は家族にとっての“道しるべ”になります。
残された家族の負担軽減
家族が一番困るのは、「どうすればよいのか分からない」ことです。
財産の把握や口座情報、保険の契約状況、介護の希望、万が一の際の連絡先など、何も情報がなければ遺された人は手探りで動かざるを得ません。精神的なショックを抱えながら、同時に実務的な対応を迫られるのはとても大変です。
エンディングノートがあれば、そうした負担を軽減できます。家族への“優しさ”としての準備とも言えるでしょう。
遺言書との違い
法的効力の有無
エンディングノートと遺言書の大きな違いは、法的な効力の有無です。
- エンディングノート: 気軽に書ける反面、法的な効力はありません。
- 遺言書: 民法に基づいた厳格な形式で作成すれば、法的な効力があります。
たとえば、遺産の分配について法的に効力を持たせたい場合は、遺言書の作成が必要になります。
反対に、
- こんなふうにしてほしい
- 家族への感謝を伝えたい
といった思いや希望は、エンディングノートが最適です。
書きやすさと活用のしやすさ
エンディングノートは、形式やルールにとらわれず自由に書けるのが特徴です。市販のテンプレートを活用しても構いません。また、自作のノートに箇条書きでまとめても構いません。
また、必要に応じて何度でも書き直すことが可能です。そのため、ライフステージの変化に合わせて内容を更新していくことができます。
一方で、遺言書は書き直すたびに形式に則る必要があります。そのため、専門家のサポートを受けることも少なくありません。
柔軟さと手軽さという点では、エンディングノートの方が取り組みやすいといえます。
何を書く?エンディングノートの主な記載項目
エンディングノートは「自由に書いていい」と言われています。しかし、「何から書けばいいのか分からない…」という声が実際によく聞かれます。実際、記載項目は多岐にわたりますが、無理なく少しずつ記入していくのがコツです。
ここでは、エンディングノートに盛り込むべき代表的な項目を3つのカテゴリーに分けて紹介します。順番に埋めていくだけでも、自分と家族の未来に備える大きな一歩になります。
基本情報・連絡先・財産情報
まず最初に記載しておきたいのは、ご自身に関する基本情報や財産の状況です。
- 本人確認情報: 氏名、生年月日、住所、本籍地、保険証番号、マイナンバーなど
- 緊急連絡先: 万が一の際に連絡してほしい家族や友人、仕事関係者など
- 財産情報: 銀行口座、通帳の保管場所、クレジットカード、年金、保険、不動産、株式や投資信託などの資産と借入れの情報
これらの情報をまとめておくことで、家族が相続や各種手続きを進める際の負担を大きく減らすことができます。
医療・介護・葬儀・お墓の希望
医療や介護、そして最期の時間についての希望も、エンディングノートに記しておくと安心です。
- 医療についての希望
- 延命治療を望むかどうか、認知症になったときの方針、緊急搬送時の希望
- 介護についての方針
- 自宅での介護を希望するのか、施設入所も選択肢に入れるのかなど
- 葬儀・供養
- 葬儀の形式(家族葬・一般葬など)、希望する葬儀社や宗派、戒名の有無、墓地・納骨堂・樹木葬などの希望
これらは、「聞きたくても聞けない」デリケートな内容です。そのためノートに残しておくことで家族が安心して判断することができます。
家族へのメッセージ・伝えておきたい思い
エンディングノートで最も大切なのは、「自分の声」として家族に思いを伝えることです。
- 家族へのメッセージ
- 感謝の気持ち、子どもたちへの人生のアドバイス、これまで伝えられなかった想い。
- 友人や恩人へのお礼の言葉
- これまでの関わりへの感謝や、思い出の記録。
- 人生の振り返りや自分らしさ
- 生きてきた軌跡を、未来の家族に伝える記録として残す。
形式にとらわれる必要はありません。一通の手紙を書くような気持ちで、あなたの“心の中の言葉”を自由に綴ってください。
エンディングノートは「一度書いて終わり」じゃない
エンディングノートは、人生の変化に応じて何度でも見直すべき「生きたノート」です。
「一度書いたから安心」と思ってしまいがちです。しかし、時間とともに状況も気持ちも変わります。
特に家族や財産に関わる内容は、定期的な更新がとても大切です。このセクションでは、見直すべきタイミングや記録方法について詳しく解説します。
更新のタイミングと見直しのポイント
エンディングノートは、次のようなタイミングで見直すのがおすすめです。
- 家族構成が変わったとき
- 結婚・離婚・出産・孫の誕生・親族の死去など。
- 資産に大きな動きがあったとき
- 不動産の購入・売却、保険の見直し、退職金の受け取りなど。
- 医療・介護に対する考えが変わったとき
- 病気を経験した、周囲の介護を見て考えが変わったなど。
- 自身の気持ちが変化したとき
- 将来の希望や価値観が変わったと感じたとき。
さらに、「年に1回、誕生日に見直す」「お正月に家族と話すきっかけとして」など、定期的な振り返りの習慣として活用するのもおすすめです。
記録すべき「更新履歴」
エンディングノートは、内容を書き直すだけでなく、「いつ、どこを、なぜ変更したか」を残しておくことも重要です。
- いつ
- 更新した日付を明記
- どこを
- 具体的に修正・追加したページや項目
- なぜ
- 変更の理由(気持ちの変化、状況の変化など)
この記録があることで、万一ご本人に確認が取れない場合でも、家族が「意図をくみ取る」ことができます。
たとえば、「以前は延命治療を希望しないと記載していたが、最新では考えが変わった」など、明確にしておくと、残された家族が迷わず判断できます。
また、更新履歴があることで、エンディングノート全体の信頼性も高まります。そして、後々の手続きにも役立つことがあるのです。
エンディングノートの保管方法と家族への共有
せっかく心を込めて書いたエンディングノートも、見つけてもらえなければ意味がありません。
また、保管方法によっては紛失や改ざん、災害による消失のリスクもあります。
このセクションでは、エンディングノートを安全に保管し、確実に家族に伝えるための工夫をご紹介します。
安全に保管するためのおすすめ場所
エンディングノートは私的な情報が多く含まれます。そのため、誰でも簡単に見られる場所に置いておくのは避けるべきです。
以下のような方法が推奨されます。
- 家庭用金庫に保管する
- 耐火・耐水仕様の金庫であれば、災害時のリスクも軽減できます。パスワードや鍵の管理にも注意しましょう。
- 鍵付きの引き出しや書類保管ケースに入れる
- ある程度アクセスしやすく、かつ不意の盗難や目隠しにもなる方法です。保管場所を信頼できる家族に知らせておくことが前提です。
- デジタル保存も有効だが注意点も
- スマホやパソコンで作成・保存する場合は、パスワードの共有・バックアップの確保が必須です。クラウド上の保存なら、ID・パスワード情報をエンディングノート本体か別紙に記載し、家族がアクセスできるようにしておきましょう。
家族・信頼できる人への伝え方
エンディングノートは、「誰かに見つけてもらえなければ」存在しないのと同じです。信頼できる家族や親しい友人に、存在と保管場所をきちんと伝えておくことが非常に大切です。
たとえば、
- 「○○の引き出しに入れてあるから、何かあったら見てほしい」と一言添えておく
- 内容までは話さなくても、「エンディングノートを書いた」という事実だけでも共有する
- 可能であれば、一緒に読み合わせをして「どんな思いで書いたか」を伝えておく
こうした事前共有があることで、遺された家族が迷わずに判断でき、心の安心にもつながります。
また、信頼できる専門家(司法書士・行政書士・FPなど)に保管を依頼する方法もあります。万が一に備えた第三者のサポート体制を整えておくのも、終活の一環といえるでしょう。
エンディングノートを始めてみよう
「いざ書こう」と思っても、どこから手をつけたらいいか迷ってしまう――そんな方は少なくありません。
しかし、エンディングノートは完璧に仕上げることが目的ではなく、「思いを残す」ことが大切です。
ここでは、初めての方でもスムーズに取り組めるおすすめのテンプレートやツール、書き始めのコツをご紹介します。
書き始めにおすすめのテンプレートやツール
まずは「書くためのきっかけ」として、手に取りやすいツールやテンプレートを使うのがおすすめです。
- 無料テンプレートを活用する
- 自治体や医療機関、金融機関などが配布している無料のエンディングノートテンプレートがあります。
- ダウンロード形式で、自宅で印刷してすぐに始められるのが魅力です。
- 市販の専用ノートを使う
- 書店や文具店で購入できるエンディングノートは、見た目も整っていて書きやすい構成になっています。
- 項目が章立てされており、手順に沿って記入できるので初心者にもぴったりです。
- スマホアプリ・クラウドサービスも選択肢に
- デジタルでの記録に慣れている方は、エンディングノート専用アプリの利用もおすすめ。
- 項目ごとの入力、写真やPDFの添付、パスワード管理など、紙のノートにはない便利な機能もあります。
書きやすいところから始めることが大切
エンディングノートは、すべてを一度に完成させる必要はありません。
- 「名前や住所などの基本情報だけでも記入する」
- 「伝えておきたい気持ちを、家族へのメッセージとして1行でも書いてみる」
- 「気になる医療の希望だけ先に考えてみる」
このように、“自分が書きやすいところから少しずつ”で大丈夫です。
書き始めることで、「あ、これも書いておいた方がいいな」と自然に考えが広がっていきます。
逆に、「書きたい気持ちはあるけれど、何から手をつければいいか分からない」という方は、テンプレートや簡単な質問形式のツールを活用することで、最初の一歩を踏み出しやすくなります。
エンディングノートは「未来の自分」と「大切な人」への贈り物
エンディングノートは、自分自身の安心のため、そして大切な人の心を守るための“やさしい備え”です。
どんなに元気でも、どんなに先のことのように思えても、「書いておけばよかった…」「知っていれば…」と後悔する声は少なくありません。
書くことで安心感が生まれる
エンディングノートは、未来に向けて自分の意思や想いを可視化する作業です。書き進めていくうちに、気持ちが整理され、不安が減っていくのを実感できるでしょう。
- 「家族にどうしてほしいか」
- 「どんな医療を望んでいるか」
- 「どんな形で送り出してほしいか」
これらを伝えておくことは、人生の最期まで「自分らしさ」を大切にすることでもあります。
家族の混乱を防ぎ、あなたの想いをしっかりと伝える手段
もしものときに、家族が判断に迷ったり、手続きで困ったりするのは珍しくありません。そんなとき、エンディングノートがあれば、「本人の想い」に基づいて行動することができるのです。
また、言葉ではなかなか伝えられない感謝や想いを文字にして残すことで、残された人の心に寄り添う、大きな支えになります。
今こそ、未来の備えとして一歩踏み出してみませんか?
エンディングノートは、何歳からでも、どんな人でも始められます。むしろ、「まだ元気な今」だからこそ、じっくりと考え、準備ができるのです。
まずは書けるところから、少しずつ。家族との会話のきっかけにもなる、あなたらしい終活を始めてみませんか?
エンディングノートに関する相談サービスもご用意しています。
「どう書けばいいか分からない」「何から始めたらいいのか不安」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
今すぐはじめる!相談はこちら
「まだ全部は書けないけど…」「書き方のイメージがわかない」そんな方のために、専門スタッフによる無料相談をご用意しています。
✅ LINEで気軽に相談したい方はこちら
👉 「LINEで無料相談する」
※スマホでタップすればすぐにつながります!
✅ 電話でじっくり相談したい方はこちら
📞 フリーダイヤル:0120-888-502(9:00〜19:00)*土日祝も対応
✅ お問い合わせフォームからも受け付けております。
エンディングノートに限らず、相続、終活全般に関するご相談はこちらもフォームからも承っております。お気軽にご相談ください。
あなたの「想い」と「準備」を、今この瞬間から。
ぜひ一歩を踏み出してみてください。私たちが全力でサポートします。