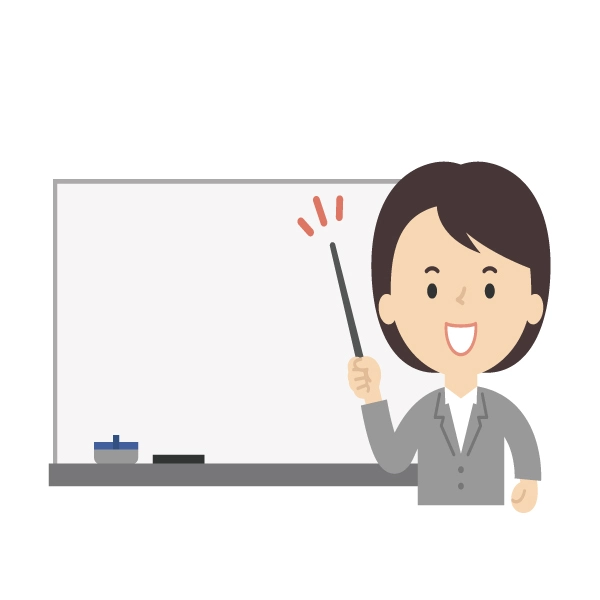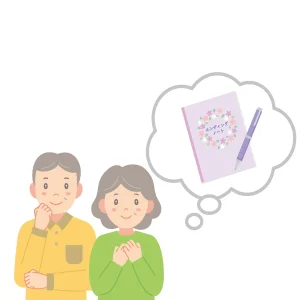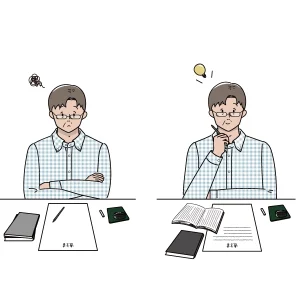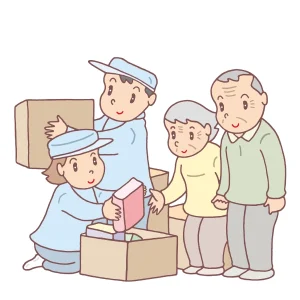生前贈与の活用方法を知ることは、「相続税が不安…」「子どもや孫に今のうちに援助したい」といった悩みを抱える方にとって、有効な選択肢となります。
- 贈与税と相続税の基本的な違い
- 生前贈与の非課税制度
これらの税の仕組みを正しく知っておけば、将来の相続税負担を軽減できるだけでなく、大切な人への想いを“今”のうちに形にすることもできます。
この記事では、生前贈与の仕組みや目的別の活用方法を解説します。さらに、注意すべきポイントまで、終活の視点からわかりやすく解説していきます。
そもそも生前贈与とは?
生前贈与とは、本人が生きているうちに自分の財産を他者に無償で譲り渡す行為を指します。
この仕組みの目的は、相続が発生する前に財産の一部または全部を計画的に譲ることで、相続税対策や家族への支援です。
「相続=死後に発生する財産の承継」に対し、生前贈与はあくまで生存中の行為です。そして、贈与のタイミングや方法を自身でコントロールできます。
そのため、近年では終活の一環として注目されています。
生前贈与の定義と相続との違い
生きているうちに財産を譲ること。これが生前贈与です。
生前贈与は、民法上「贈与契約」として成立するものです。そのため、贈与者(財産を渡す人)と受贈者(受け取る人)の双方の合意によって行われます。その最大の特徴は、「自由に贈与先を選べる」という点です。
相続が法定相続人に自動的に分配されるのに対し、生前贈与では相手を限定することが可能です。
たとえば、
- 孫だけに教育資金を贈りたい
- 特定の子どもに自宅を譲りたい
このように相手を自由に選ぶことができるのです。そんな希望を叶える柔軟性が生前贈与の大きな利点です。
しかしその一方で、贈与には贈与税がかかる場合があるため、事前の制度理解が欠かせません。
なぜ生前贈与が終活で注目されているのか
- 相続税の節税対策になる
- 財産の使い道を見届けられる
生前贈与が終活で注目される最大の理由は、相続税の節税効果が期待できるからです。
相続税は、相続財産が一定額(基礎控除)を超えた場合に課税されますが、生前贈与を活用して財産を事前に減らしておけば、その課税対象自体を減らすことが可能です。
さらに、「誰に、どれくらいの財産を、どんな目的で渡したいのか」を自らの意思で実現できる点も魅力です。
たとえば、
- 孫の教育資金
- 結婚資金の援助
- 不動産の早期承継
など、目的を持った贈与が可能になります。
その使われ方を生きているうちに見届けられる点は、心理的な満足感も大きいでしょう。
★関連記事:相続税対策とは?基礎控除の計算・節税対策・今すぐ相談すべき理由を解説!
目的別、生前贈与の活用方法
生前贈与は、ただ財産を渡すだけではありません。その目的によって使い方が大きく異なります。
ここでは、代表的な4つの活用方法を紹介します。家族構成や資産の内容に応じて、最適な方法を選ぶことが重要です。
110万円の非課税枠を毎年使う「暦年贈与」
- 継続的な贈与で相続財産を減らす
- 複数人に贈与することで効果が大きく
最も基本的な方法が、毎年110万円まで非課税で贈与できる「暦年贈与」です。贈与税の基礎控除枠を活用することで、税負担なく資産を少しずつ移転できます。
この方法は、時間をかけてコツコツ相続財産を減らしたい場合に有効です。
例えば、子や孫が3人いれば、それぞれに毎年110万円ずつ贈与することで、年間330万円の資産移転が非課税で可能になります。
ただし、形式的な「名義貸し」にならないよう、贈与契約書の作成や実際の受け取り(通帳・印鑑管理)を相手方に任せるなど、証拠を残すことが重要です。
教育資金・結婚・子育て資金の一括贈与
- 特例制度を使えば最大1,500万円まで非課税
- 孫世代への支援として人気
子や孫の将来を支援したいと考える方には、「教育資金の一括贈与」や「結婚・子育て資金の一括贈与」制度の活用が適しています。これらの制度を使えば、最大1,500万円(教育)または1,000万円(結婚・子育て)まで非課税で贈与できます。
銀行等で専用口座を開設し、支出ごとに領収書を提出するなど、一定の手続きが必要ですが、「まとまった資金を非課税で渡せる」点は大きな魅力です。
贈与された資金が実際に使われたことを確認できるため、贈与者も安心して支援できる点もポイントです。
不動産・株式などの資産移転
- 高額資産は早めに贈与で評価額圧縮
- 将来の売却や運用も見据えて計画
不動産や上場株式といった高額資産は、将来の相続税の対象になりやすいため、早めの生前贈与で評価額の圧縮を図るのが有効です。
特に、不動産は時価よりも低く評価される場合が多く、相続時よりも贈与時の方が課税評価額が低く抑えられる可能性があります。また、将来的に売却や賃貸などの運用を予定している場合には、早期に名義を移しておくことでスムーズに対応できます。
ただし、登録免許税や不動産取得税が発生します。そのため贈与の前に費用シミュレーションを行うことが必要不可欠です。
★関連記事:相続不動産売却をお勧めする理由と後悔しないに知っておくべきこと
贈与と相続を組み合わせる「生前対策信託」
- 信託契約を利用して財産の運用管理を託す
- 認知症リスクにも備えられる
近年注目されているのが、「生前対策信託(家族信託)」の活用です。
これは、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・運用を託す仕組みで、将来の相続や介護を見据えた柔軟な対応が可能になります。
たとえば、不動産を長男に託し、家賃収入を父が受け取る。このように、所有と管理を分けることができるのが特徴です。認知症による資産凍結リスクの回避にもつながり、財産管理における「備え」として有効です。
ただし、信託契約書の作成や登記が必要であるため、専門家の関与が不可欠です。
★関連記事:終活の新常識!家族信託の活用で安心の相続計画を実現する方法
生前贈与の注意点と落とし穴
生前贈与は非常に有効な相続対策です。しかしながら、制度を正しく理解していないと「贈与がなかったことになる」「余計な税負担が発生する」といった思わぬトラブルにつながることもあります。
ここでは、特に注意すべき2つのポイントをご紹介します。
贈与税の申告漏れに注意
- 非課税枠を超えたら申告が必要
- 領収書や契約書の整備も重要
生前贈与で最も見落とされやすいのが、贈与税の申告漏れです。110万円の非課税枠はあくまで「年間の合計額」に対して適用されるものです。ですので、非課税枠を超えた贈与には必ず贈与税の申告が必要になります。
たとえば、親から子に150万円を贈与した場合、そのうち110万円を除いた40万円について申告が求められます。申告を怠ると、後から税務署の調査が入り、追徴課税や延滞税の対象になることも想定されます。
また、贈与を証明するための「贈与契約書」や、資金の移動を記録した通帳コピー・領収書などのエビデンス(証拠資料)をきちんと整備することが重要です。
贈与契約書には、贈与する金額・目的・時期などを明記し、署名・押印しておきましょう。
名義預金・贈与の“つもり”になっていないか
- 実態のない贈与は否認されるリスクあり
- 通帳・印鑑・意思表示の管理を徹底
もう一つの落とし穴は「名義預金」の問題です。これは、贈与者が自分の名義で貯金をしながら、形式的に相手の名義にしている状態のことです。実際には贈与が成立していないにもかかわらず、「贈与したつもり」で処理してしまうケースが多く見られます。
たとえば、子供名義の口座に親が勝手にお金を移して、通帳や印鑑も親が管理している場合、税務署からは“贈与ではない”と判断され、相続財産とみなされるリスクがあります。
これを防ぐためには、贈与された側(受贈者)が通帳・キャッシュカード・印鑑を自分で管理することです。そして、自分の意思でお金を使える状況を整えることが大切です。
また、贈与されたことを受贈者が理解し、同意しているという意思表示の記録も、贈与の成立を証明するうえで重要になります。
生前贈与を成功させるコツ
生前贈与は、やみくもに始めるのではなく「目的」と「計画」に基づいて進めましょう。そうすれば、その効果を最大限に引き出すことができます。
節税・資産移転・家族への支援という視点を持ち、確実でトラブルのない贈与を実現するためには、次の2つのポイントがカギになります。
目的に応じた「贈与の設計」がカギ
- 誰に・何を・いつ・どう渡すかを明確に
- ライフプランと贈与プランを連動させる
贈与を成功させるためには、まず「誰に・何を・いつ・どのように渡すか」を明確にする必要があります。たとえば、孫の進学資金として使ってもらいたいなら、教育資金一括贈与の非課税制度を活用するといった具体的なプランニングが重要です。
また、贈与は一度に大きな財産を移すのではなく毎年の非課税枠(暦年贈与)を活用して少しずつ贈ることで税負担を軽減できます。贈与の目的(教育支援、住宅取得支援、資産分散など)と、自身の老後資金のバランスを見ながら進めることが重要です。
このように、ライフプラン(老後資金・介護費用など)と贈与プランを連動させることで、安心して贈与を進めることができます。
専門家のサポートを活用する
- 税理士・司法書士による契約・申告のサポート
- 相続全体の視点でのアドバイスが得られる
生前贈与は、税務や法務の知識が求められる場面が多くあります。
たとえば、
- 贈与契約書の作成
- 贈与税の申告
- 名義変更
- 不動産登記
など、正確な手続きを行うには専門知識が必要です。
そこで活用したいのが、税理士や司法書士、行政書士といった相続に強い専門家のサポートです。
贈与契約や申告に加えて、将来の相続を見据えた全体的な資産管理や遺産分割計画のアドバイスを受けることができるのが大きなメリットです。
特に、不動産や自社株式など高額資産の贈与を検討している場合は、信託制度や法人化などのスキーム提案を受けることで、さらに賢く、そして円滑な贈与が可能になります。
生前贈与の活用方法で「想い」と「財産」を次世代へ
生前贈与の活用は、単なる節税テクニックではありません。
大切なのは、
- 「自分の財産をどう託すか」
- 「家族にどんな形で想いを届けたいか」
という気持ちをかたちにする手段であるということです。
贈与によって、今のうちに支援したい人をサポートできます。また、将来の相続トラブルや税負担の軽減にもつなるのです。
そして何より、生きているうちに家族の笑顔や感謝の言葉を受け取れる喜び。これが大きな魅力ではないでしょうか。
「まだ早い」と思って後回しにせず、今日からできる一歩を踏み出すことが、あなたと家族の安心を築くカギになります。
LINEで生前贈与・相続の無料相談受付中!
- 「どれくらい贈与してもいいの?」
- 「うちの財産ならどう活かせる?」
そんな疑問をLINEで気軽に相談してみませんか?
贈与税や相続税の不安、家族との財産共有、老後のライフプラン設計まで経験豊富な専門家があなたの状況に合わせて丁寧にアドバイスいたします。
\贈与・節税・家族との共有に関するお悩みを解決します/
👉[LINEで無料相談する]